- 個人事業主のための損害賠償基礎知識 - TOP
- >
- 損害賠償で抑えるべき知識
- >
- 損害額の算定と立証のポイント
 個人事業主として活動する中で、損害賠償請求を行う場合や請求される場合において、最も重要でありながら困難を伴うのが損害額の適正な算定です。法的な要件を満たしていても、損害額の算定や立証が不十分であれば、適切な賠償を受けることはできません。逆に過大な請求は信頼性を損ない、裁判でも不利に働く可能性があります。
個人事業主として活動する中で、損害賠償請求を行う場合や請求される場合において、最も重要でありながら困難を伴うのが損害額の適正な算定です。法的な要件を満たしていても、損害額の算定や立証が不十分であれば、適切な賠償を受けることはできません。逆に過大な請求は信頼性を損ない、裁判でも不利に働く可能性があります。
損害賠償における損害額の算定は、客観的かつ合理的な根拠に基づいて算出される必要があり、裁判所が納得できる論理的な説明が求められます。
損害は大きく「積極損害」と「消極損害」に分類されます。積極損害とは実際に支出を余儀なくされた費用で、システム障害の復旧費用や代替手段の調達費用などが該当し、領収書や請求書で比較的立証しやすいものです。一方、消極損害とは本来得られるはずだった利益の喪失、いわゆる逸失利益を指し、個人事業主にとっては算定が困難となります。
個人事業主の逸失利益算定では、過去の実績に基づく客観的な根拠が最も重要です。固定給がないため、「本来得られたはずの収入」を立証するには、過去の売上実績、契約書、取引先からの証明書など複数の資料を組み合わせることが不可欠です。単に収入額を主張するだけでは不十分で、その収入が継続的かつ安定的なものであったことを示す必要があります。
損害の発生期間についても慎重な判断が必要で、一時的な障害による短期間の損失か、継続的な影響による長期間の損失かによって算定方法は大きく異なります。
損害賠償請求において、損害の存在とその金額を立証する責任は原則として請求する側が負います。この立証責任を果たすためには、日頃からの証拠保全が極めて重要になります。
個人事業主にとって最も重要な証拠は、日頃からつけている帳簿や会計資料です。青色申告の複式簿記による記録は特に高い証明力を持ち、売上台帳、経費明細、銀行取引記録などは損害額算定の基礎資料として不可欠です。これらの記録が正確で継続的につけられていることが、損害額の信頼性を大きく左右します。
数字だけでなく、その正確性を裏付ける資料も必要です。請求書、領収書、契約書、取引先とのメールのやり取りなど、取引の実態を示す資料を体系的に保管しておくことが重要です。継続的な取引では、取引開始時の経緯や契約条件の変更履歴を時系列で整理しておくと立証に役立ちます。
現代ビジネスではデジタル証拠の重要性が増していますが、改ざんの可能性があるため適切な保全方法が必要です。重要なメールの印刷保管、タイムスタンプサービスの活用、第三者機関による証拠保全サービスの利用などの方法があります。
個人事業主が損害額を算定する際には、法人とは異なる特有の注意点があり、これらを理解していないと過大請求や過小評価を招く可能性があります。
最もよくある間違いが、売上減少をそのまま損害額として計上することです。法的に認められる損害は原則として「利益」の減少分であり、売上から必要経費を差し引いた純利益部分が実際の損害額となります。月売上100万円の減少があっても、材料費や外注費などの変動費を差し引いた実際の利益減少額が損害額になります。
固定費と変動費の区別も重要です。売上減少でも削減できない固定費(事務所賃料、保険料など)と、売上に連動する変動費(材料費、外注費など)を適切に分類し、実際の利益減少額を正確に算出する必要があります。
将来逸失利益については特に慎重な算定が求められます。過去の取引実績があっても、将来も同様の取引が継続されたであろう蓋然性を客観的に示す必要があり、過去の取引期間や安定性、市場環境を総合的に勘案して合理的な期間を設定することになります。
複雑な損害額算定では、税理士や公認会計士などの専門家の意見書を取得することも有効で、第三者による客観的な算定は裁判所でも高い信頼性を持って評価されます。

プロジェクトの成否を分けるのは、着手前の準備の質です。特に個人事業主にとって、リスクアセスメントは損害賠償トラブルを防ぐ重要な防衛線となります。ここでは、プロジェクト評価のチェックポイントや要件定義での注意点、契約時の確認事項など、実践的なリスク管理手法を紹介します。システム開発特有の不確実性に対応するため、具体的な評価基準とチェックリストを用いた体系的なリスク管理方法について詳しく解説していきます。more
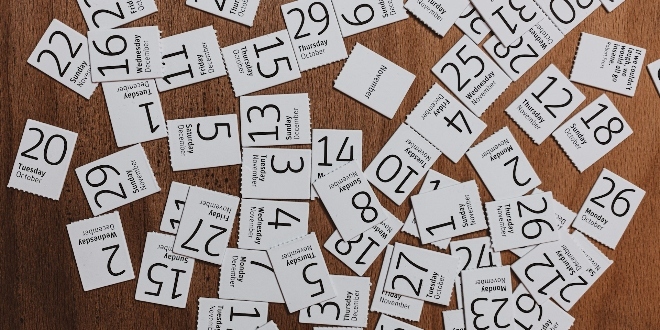
個人事業主にとって、納期厳守は信頼関係維持と損害賠償リスク回避のために不可欠です。納期遅延は相手方に迷惑をかけ、ビジネスにも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、余裕のある納期設定が重要です。これにより突発的なトラブルにも対応でき、質の高い仕事につながります。また契約書の作成も重要で、納期や報酬額だけでなく、予期せぬ事態への対応も明記すべきです。専門家の意見を聞くことで、より詳細な契約内容を盛り込むことができます。これらの対策により、個人事業主は長期的に安定した活動が可能となります。more

損害賠償で訴えられた場合にも、慌てて対処を間違えると、何ら落ち度がないのに高額の賠償を支払わなければならなくなる危険があり、注意が必要です。まず訴状が届いたら、原告の請求を認めない旨を記載した答弁書を提出します。こうしておけば、第一回目の期日に欠席しても、不利にはなりません。そして原告の主張と立証を基に、戦略を立てます。仮にその事件と関連して逆に請求できるものがあれば、反訴を提起することも可能です。more