- 個人事業主のための損害賠償基礎知識 - TOP
- >
- 損害賠償で抑えるべき知識
- >
- 請求手続きの方法
 ビジネス上の取引関係において、こちらに何ら落ち度がないにもかかわらず、損害を被ったような場合、特に個人事業主であれば、取引先との力関係やその他のやむに已まれぬ事情によって、泣き寝入りする場合も少なくないのが現実です。日本の社会では、欧米とは異なり、和を乱さずに事を穏便に済ませようという意識が働きがちなものですが、たとえ継続的な取引関係であっても、要求すべきことは要求しなければならない時があります。
ビジネス上の取引関係において、こちらに何ら落ち度がないにもかかわらず、損害を被ったような場合、特に個人事業主であれば、取引先との力関係やその他のやむに已まれぬ事情によって、泣き寝入りする場合も少なくないのが現実です。日本の社会では、欧米とは異なり、和を乱さずに事を穏便に済ませようという意識が働きがちなものですが、たとえ継続的な取引関係であっても、要求すべきことは要求しなければならない時があります。
まず損害が発生した時にも、最初から強硬な姿勢に出るのではなく、当事者同士の話し合いで解決するよう働きかけることが肝要です。というのも感情のもつれから、小さな問題が大きくなってしまうと、引っ込みがつかずに双方にとって益になることはないからです。
しかし相手方が一切聞く耳を持たないなど、損害賠償の請求に応じて素直に支払おうとしない場合には、法的手続きを採る準備に移ります。ここでもいきなり訴訟を提起するのではなく、まずは内容証明郵便を送ります。これは当事者名義で送ることも可能ですが、あまりインパクトがありません。そのため弁護士に相談して、弁護士名で内容証明郵便を送って様子を見ると良いでしょう。法的手段も辞さないという強い決意を相手側が読み取って、早期解決を図るために賠償に応じることがあります。
そしてこの内容証明は、後々裁判となった場合にも、その時点ではっきりと相手に賠償請求の意思を伝えたという証拠になります。
弁護士に相手との示談交渉も依頼するのであれば、相手方の言い分を聞きながら妥当な解決策を模索して、交渉がまとまれば和解契約を結ぶなど、損害賠償の方法や時期や金額など、詳細を明確に書面にします。この際万一この義務を相手が守らない場合に備えて、公正証書を作成したり、即決和解にすることもあります。
当事者同士では解決がつかない場合にも、調停を申し立てて、調停員という第三者を間に挟んで話をまとめる方法があります。当事者同士では感情的になってしまうことも、第三者を通じると案外話がまとまることもあります。しかし費用が安くて済むものの、飽くまで訴訟手続きではないため、相手方に出席を強要することはできません。
従ってお互いに話し合いで解決するつもりがあるが、金額や支払時期などを詰める必要がある場合などでなければ、不調に終わることが少なくありません。
そして最後の手段が、訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐというものです。双方の主張立証を尽くすため、費用も時間もかかります。もっとも判決に至るよりも、裁判上あるいは裁判外の和解で終わる例の方が多いのも事実です。

プロジェクトの成否を分けるのは、着手前の準備の質です。特に個人事業主にとって、リスクアセスメントは損害賠償トラブルを防ぐ重要な防衛線となります。ここでは、プロジェクト評価のチェックポイントや要件定義での注意点、契約時の確認事項など、実践的なリスク管理手法を紹介します。システム開発特有の不確実性に対応するため、具体的な評価基準とチェックリストを用いた体系的なリスク管理方法について詳しく解説していきます。more
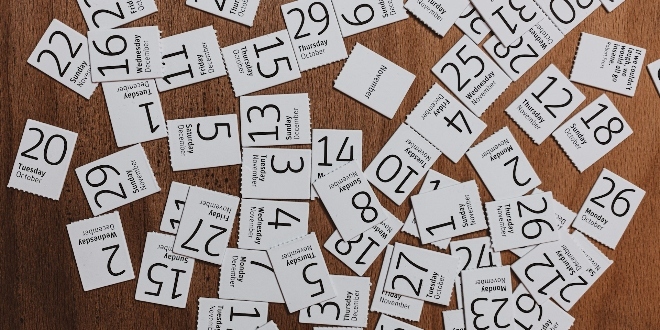
個人事業主にとって、納期厳守は信頼関係維持と損害賠償リスク回避のために不可欠です。納期遅延は相手方に迷惑をかけ、ビジネスにも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、余裕のある納期設定が重要です。これにより突発的なトラブルにも対応でき、質の高い仕事につながります。また契約書の作成も重要で、納期や報酬額だけでなく、予期せぬ事態への対応も明記すべきです。専門家の意見を聞くことで、より詳細な契約内容を盛り込むことができます。これらの対策により、個人事業主は長期的に安定した活動が可能となります。more

損害賠償で訴えられた場合にも、慌てて対処を間違えると、何ら落ち度がないのに高額の賠償を支払わなければならなくなる危険があり、注意が必要です。まず訴状が届いたら、原告の請求を認めない旨を記載した答弁書を提出します。こうしておけば、第一回目の期日に欠席しても、不利にはなりません。そして原告の主張と立証を基に、戦略を立てます。仮にその事件と関連して逆に請求できるものがあれば、反訴を提起することも可能です。more