- 個人事業主のための損害賠償基礎知識 - TOP
- >
- 損害賠償で抑えるべき知識
- >
- 訴訟を起こされた時の対処法
 ビジネスにトラブルはつきものです。自らに落ち度がなくても、取引先に損害が発生して、賠償を請求されるかもしれません。しかしそもそもの契約内容が曖昧で、契約書も取り交わしていない場合が多く、中には言いがかりをつけられたり、責任を押し付けられるということも無いとは言えません。ある日突然裁判所から訴状が送られてくれば、誰しも慌ててしまいます。中には、面倒なことには一切関わりを持ちたくないと、届いた書類を開封せずに放置してしまう人もいるようですが、対応を誤ると思わぬ不利益を被る場合もあり、冷静な対処が必要です。
ビジネスにトラブルはつきものです。自らに落ち度がなくても、取引先に損害が発生して、賠償を請求されるかもしれません。しかしそもそもの契約内容が曖昧で、契約書も取り交わしていない場合が多く、中には言いがかりをつけられたり、責任を押し付けられるということも無いとは言えません。ある日突然裁判所から訴状が送られてくれば、誰しも慌ててしまいます。中には、面倒なことには一切関わりを持ちたくないと、届いた書類を開封せずに放置してしまう人もいるようですが、対応を誤ると思わぬ不利益を被る場合もあり、冷静な対処が必要です。
訴訟の提起は、原告が裁判所に訴状を提出することから始まります。裁判所は受け取った訴状に不備がなければ、それを被告宛てにも送達します。実際の裁判は原則として、口頭弁論期日に、原告被告の双方が出頭し、お互いの主張と立証を繰り広げることになっています。
しかし被告が答弁書も提出せずに、第一回期日に欠席すると、原告の主張に理由があると認められれば、そのまま被告の敗訴が決まってしまう危険があります。従って訴状を受け取った場合には、すぐにも「原告の請求は認められない」という内容の答弁書を、裁判所に提出する必要があります。
この最初の答弁書には詳細な否認の理由や反論を述べる必要はありませんし、答弁書を提出してさえいれば、勝手に日時を決められた第一回目の期日を欠席しても問題ありません。
訴状には、原告の主張が記されていますが、逆に言えば原告の主張しか記されていません。訴えられた側の言い分は、訴えられた側が主張しなければならないのであり、反論や反証があれば、自ら示さなければなりません。
しかしあくまで原告の主張を崩すことができればよいのであり、従って訴状や準備書面などから、原告の主張とその証拠をよく見極めて、どのように訴訟を進めれば有利になるか、戦略を練ることが必要です。また裁判の過程において、しばしば裁判官からの和解の勧告を受けることがあります。何が何でも争う決意の場合は別ですが、この際訴訟を継続するメリットとデメリットとの兼ね合いから、思い切ってお金で解決してしまうというのも一つの方法です。
もっとも話し合いである以上、逆に原告の請求に全く反論の余地がない場合であっても、和解を有利に進めることは可能です。
そして原告が訴訟を提起した以上、その事案に一定の関連がありながら、請求していない権利があれば、この際反訴として請求するのも一つの戦略です。逆向きの請求に関する二つの紛争も、一定の関連があるために、一つの訴訟の場で解決することが可能になるという制度であり、主張や証拠が共通する面もあるため訴訟経済上も効率的なのです。

プロジェクトの成否を分けるのは、着手前の準備の質です。特に個人事業主にとって、リスクアセスメントは損害賠償トラブルを防ぐ重要な防衛線となります。ここでは、プロジェクト評価のチェックポイントや要件定義での注意点、契約時の確認事項など、実践的なリスク管理手法を紹介します。システム開発特有の不確実性に対応するため、具体的な評価基準とチェックリストを用いた体系的なリスク管理方法について詳しく解説していきます。more
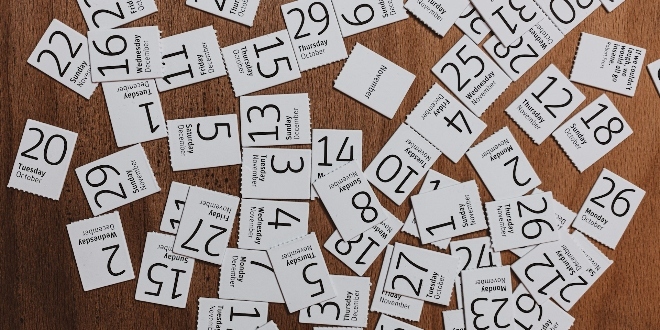
個人事業主にとって、納期厳守は信頼関係維持と損害賠償リスク回避のために不可欠です。納期遅延は相手方に迷惑をかけ、ビジネスにも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、余裕のある納期設定が重要です。これにより突発的なトラブルにも対応でき、質の高い仕事につながります。また契約書の作成も重要で、納期や報酬額だけでなく、予期せぬ事態への対応も明記すべきです。専門家の意見を聞くことで、より詳細な契約内容を盛り込むことができます。これらの対策により、個人事業主は長期的に安定した活動が可能となります。more

損害賠償で訴えられた場合にも、慌てて対処を間違えると、何ら落ち度がないのに高額の賠償を支払わなければならなくなる危険があり、注意が必要です。まず訴状が届いたら、原告の請求を認めない旨を記載した答弁書を提出します。こうしておけば、第一回目の期日に欠席しても、不利にはなりません。そして原告の主張と立証を基に、戦略を立てます。仮にその事件と関連して逆に請求できるものがあれば、反訴を提起することも可能です。more